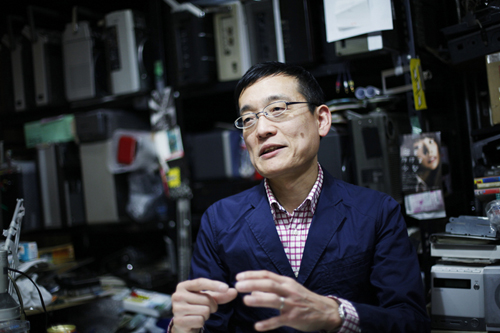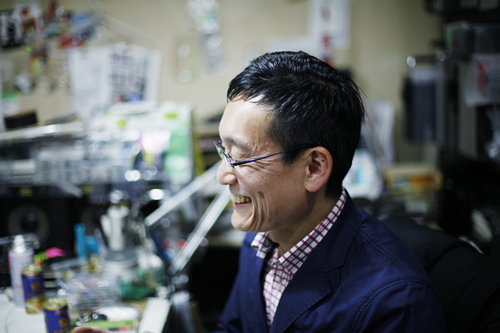日本でただ1人、自身を"家電蒐集家"と名乗る松崎順一さん。都心から約1時間、のどかな雰囲気漂う足立区にファクトリーを構えながら、日々日本中を駆け巡る根っからの家電マニア。ラジカセに始まり、テレビやスピーカー、オーディオ機器に至るまで、数えきれない家電の山を相手に日々孤軍奮闘する、彼の半生を根掘り葉掘り訊いてきました。
Photo_Kengo Shimizu(STUH)
Edit_Jun Nakada
-まず松崎さんの生い立ちから聞いていいですか?
松崎順一(以下松崎/敬称略): はい、生まれは台東区の三ノ輪という下町で、4歳のときに足立区に引っ越してきて、それから中学・高校と埼玉に引っ越したんですけど、20歳過ぎて僕だけまた戻ってきて......。そのままずっと足立区に住んでます。
-足立区が大好きなんですね。
松崎: 基本的に小さい頃から住んでいるからというのもありますけど、足立区自体が東京都でありながら東京都でないようなユルさがあるというか、ほのぼのしているんだけど変な人が多くて、俗に"ヤンキー天国"と言われてるぐらいですからね。治安は悪いけど、東京の中でも独特の雰囲気を醸し出している街ですよ。
-確かに僕の友達にも足立区出身の悪いヤツがいます......
松崎: あとココを拠点に活動している一番の要因は、蒐集するポジションとして足立区を中心にまわるのが一番効率的ということ。
-そそ、そこです、聞きたかったこと!
松崎: (笑)。東京の場合、家庭や会社、企業から出たゴミが集められて廃棄される場所が、大体埼玉県や千葉県とか、関東近県の道路が整備されていて、車で運びやすいところにあるんですけど、そこって足立区からアクセスがメチャクチャいいんですよ。仮に都内の真ん中で活動していると、打ち合わせとかはいいんですが、蒐集するときに都内を抜けるのにすごく時間がかかるんです、特に平日とか。だから足立区は色んなとこへ行くのに一番適しているんです。
-東京、埼玉、千葉を結ぶ中心地ということですね。
松崎: はい。足立区って活動エリアと蒐集エリアのちょうど中間なんです。だから原宿や青山へ出るのも40~50分くらい。逆に蒐集しに行くところも大体30~40分圏内なんです、千葉でも埼玉でも。だからすごく理に適っている。たまたまずっと足立区に住んでいるけど、蒐集活動をするのに、実はこれほど適した場所はないっていう。後になって気付きましたね(笑)
-なるほど、足立区生まれが功を奏したと。ちなみに幼少時代はまだ蒐集に目覚めていなかったんですか?
松崎: うん。20歳ぐらいまで蒐集は一切していないですね。でも、いわゆる家電小僧でした。小学生のときから秋葉原に行って部品を買ってラジオやトランシーバーを作ってみたり。
-"機械いじり"が好きだった。
松崎: そうそう。それで中学生の時にラジカセ買ってもらってずっと遊んでたんです。放送局ごっこやったり深夜放送をずっと聴いてたり。それで高校生になってアマチュア無線を始めて。俗にHAM(ハム)と言いますが、知らない人と交信するんです。そのためにアマチュア無線技師の資格を取ってからというもの、ずっと家でトランシーバー片手に勉強もしないで世界中の人と交信をしてましたね。
-トランシーバーの電波って海外まで届くものなんですか?
松崎: 世界中のどこでも届くんですよ。当時だから、今から40年ぐらい前ですかね、中学生のときに世界中の人と話していたんですよ。
-相手はどんな人か分からないんですよね?
松崎: もちろん。アマチュア無線をやっている人は日本に何十万人もいて。さらにそれを超える数の人たちが世界中にいるんです。周波数帯というのが国際的に決められていて、海外と交信したいのであれば、送受信可能なトランシーバーを買って、家にアンテナを付ければすぐにできるんですよ。
-なんか規模が大きすぎてイメージ湧かないですね。
松崎: そういうのを中学、高校のときにやっていて。勉強もろくにしてなかったので成績がすごく悪くて(笑)。でも英語だけは抜群でした。だって英会話だけは無線で散々交信してましたから。ネイティヴの人と話せたのですごくためになりましたね。
-今の世の中でいうSNSに似てますね。
松崎: そうそう。一番面白いのが不特定多数の人と交信できるということ。誰だか分からない人と初めて会って(話して)、その場で友達になっちゃうんです。話が合えばまた今度会いましょうって。
-なんかロマンがあるなぁ。
松崎: そうなんですよ。誰と話すか分からない、誰と出会うか分からない、そういう出会いのワクワク感がアマチュア無線にはあるんです。SNSの場合、少なくともどちらかは相手を知ってて始まるじゃないですか。無線は誰かは分からないけど、話が合えば友達になっちゃうっていうのが面白いんです。それで交信が終わったら、記録としてQSLカードというのが発行されて家に届くんですけど、毎月何百人と交信していたので、その量は半端じゃなかったですね。ちなみに女性でやっている人がいると、男性がみんなその人に群がって(笑)
-今でもアマチュア無線の文化は続いているんですよね?
松崎: もちろん続いてますよ。蒐集の仕事を始めてから無線関係の人とも知り合いになって。またやりましょうよって話が盛り上がったり。今これだけ携帯電話とかSNSで、色んな人と簡単に話せる時代だけど、無線で誰だか分からない人と交信するのって、今でもすごくロマンがあるなって思うわけです。それこそ昔よりやっている人の数は減りましたけど、アマチュア無線自体はちゃんと残ってます。秋葉原にもいくつか無線機を売っているお店があるし。かなりコアなお店ですけど、それはそれで楽しい。僕は無線で話すのもいいけど、操作する行為がもっと好きなんです。スイッチをパチパチ入れてヘッドフォンしてマイクして、どこかに面白い人いないかなって、キュッキュってやって。自分から話すこともあるし、向こうから話してくることもあるし。あとは声だけじゃなくて電信とかモールス信号でも交信してましたね。
-なんかCIAみたいですね。
松崎: そうそう、昔のスパイ映画みたいでしょ。子供心と男心を同時にくすぐる感じ。こういう機械で交信するのってなんかカッコいいじゃないですか。
-女の子にそのカッコよさは分からないかもしれませんね(笑)
松崎: そう。でも女の子の中にも無線好きの子がいて、そういう子に憧れたんですけどね。当時は無線をやってる人って、いわゆるオタクなんですけど、そういうアイドル的な女性も当時結構いましたね。
-アマチュア無線以外に部活はしてなかったんですか?
松崎: 誘われたんですけど結局帰宅組。学校が終わると真っ先に帰ってすぐに無線機のスイッチをパチパチっと入れて(笑)。世界中と交信するから、必ずどこかの国から信号が出てるんですよ。どこかが夜で、どこかが昼だから。だから家には24時間用の時計を置いて交信してました。
-大学もずっとアマチュア無線にハマっていたんですか?
松崎: デザイン系の専門学校だったんですが、勉強が忙しくなって無線からは離れましたね。そもそも僕が決めたというよりは、親がね......。無線ばかりやってたから手に職つけろって言われて。それだったら設計ができて、絵も好きだったから、じゃあデザインなら食いっぱぐれないんじゃないかってことで。それで卒業後はインテリアがメインの会社に就職して、約22年間、空間デザインやイベントのブースデザインとか、あとはショーウインドウのディスプレイを手掛ける仕事をずっとやってました。
-親の一声とはいえ、かなり長く続いたんですね。
松崎: そうですね。それはそれで面白かったですからね。で、30後半ぐらいになってから、このまま会社で一生終わるのは嫌だなと思うようになって。それなら自分の好きなことやりたいなって。そしたらたまたま37歳の時に交通事故で背骨を粉砕骨折してしまって。全治6ヶ月。首のところから腰まで両側ギブスで丸3ヶ月間入院ですよ。最初、病院に担ぎ込まれたときに、99%車椅子か生きているだけで幸運ですって言われて。ものすごく重症だったんですけど、結局手術もしないで、半年間ギブスだけで治っちゃったんです。たまたま粉砕したのが神経から一番遠いところの骨で。一番いいところが粉砕したねって医者にも言われて(笑)。本当に半年間ただただ寝ているだけでした。
-その間に人生を振り返ったわけですね。
松崎: そうそう、人生って儚いなって。考え方が変わりましたね。このまま仕事をやっていてどうなのかなって。それで40歳を過ぎたときに、このままじゃいけないと思って突然会社を辞めたんです、1回リセットさせてくださいって。リストラでもなんでもないんですけど、上司や社長にも"なに馬鹿なこと考えてるんだ"って止められて。でも42歳のときに強引に辞めて......。古いものを集めるにはどうすればいいのか、そこから勉強しようって。
-蒐集に関して予備知識はあったんですか?
松崎: まったくのゼロです。まずは1年間かけて僕の知り合いがやっているリサイクルショップで見習いとして働かせてもらって。そこで古いモノの流通がどうなっているのか、まず業界を覚えることから始めました。まさか42歳で軽トラに乗って廃品回収するとは思ってなかったですね(笑)。ショップに電話がかかってきて、こういうものを買い取ってください、処分してくださいって言われると、ハイハイって車走らせて。仕入れから値付けまで、業界の仕組みを全部学びました。で、約1年間自分なりに勉強して古物商の免許も取って、2003年に「DESIGN UNDERGROUND」をスタートしました。最初は家の近所の八坪くらいの小さいところで、僕のコレクションの一部を売っていたんです。
-ショップからのスタートなんですね。
松崎: うん、それが誰の通らないような質素な場所だったせいか、本当に誰も来なくて(笑)。それでショップってなんか違うなと思って、自分のホームページを作ったりしつつ、徐々にいろいろな人に広まっていった感じかな。そうしているうちに、修理をお願いされたり、昔の家電をイメージビジュアルで使いたいとか、要望が来るようになって。その時に、"こういうことが仕事になるんだ"って思うようになって。それから小さい倉庫を借りて、全部モノを移して。2年間ぐらいは、倉庫にモノを置いてウェブだけでやっていたんです。
-それから徐々に仕事のスタイルや幅が広がったわけですね。
松崎: そう。ラジカセはずっと扱っていたんですけど、それ以外の家電を取り扱うようになったのは、今から5年くらい前。だからショップを開いてからほぼ5年間は、箸にも棒にも引っ掛からなくて本当に無名の存在でした。
-ファッション業界とも接点があるようですね。
松崎: 今はファッション関係の仕事もさせてもらっていますが、最初はファッションじゃないんです。千葉市にある子供科学館のディスプレイの仕事で、たまたま僕のホームページを見て、「昔の家電を今の子供たちに紹介したいんだけど、そういう専門家がいないのでやってくれませんか?」って。で、科学館に収める家電を集めて、直したり、別の作品を作ったりするのに、今の場所をファクトリーとして借りたんです。だから当時は何もなかったんです。この作業机と少しの家電だけでしたね。
-実際何を作っていたんですか?
松崎: 子供が遊べるような電子オブジェみたいなものですね。秋葉原にあるようなパーツを使って、それを壁にいっぱい埋めて。声を出したり動くと画面が切り替わったり、いろいろなインスタレーションが楽しめるオブジェを作りました。それと古い家電も僕のコレクションの中から探して何百個も納めました。古い家電や、歴代の家電を見るコーナーとか。いろいろ作らせてもらいましたね。それが初めての大きな仕事でした。
-こども科学館がきっかけに広がっていったと。
松崎: そうですね。ファッション関係での初めての仕事でいうと、2年前のクリスマスに、エルメス各店のディスプレイをやらせていただいたことです。全店ではないんですけど、渋谷西武や横浜高島屋とか何店舗かで。昔のテレビとかアンティークの木のテレビを店内の中央に重ねてクリスマスツリーのように配置して。で、それぞれのテレビにコレクションの映像を流すっていう。ザラッとした質感の画面にコレクションが映るのがすごく良くて。それを色んな人に見てもらって、他のブランドからも依頼が来るようになりましたね。昨年の12月には〈AZUL by moussy〉と一緒に、表参道の東急プラザ1階にあるSHELTER TOKYOのクリスマスディスプレイをやらせていただきました。あとこれも去年ですが、BEAUTY&YOUTHさんと〈C.E〉のポップアップストアも手伝わせていただきました。
-Skatethingさんから直々に依頼が来たんですか?
松崎: そうなんです。もうビックリ。〈C.E〉の期間限定のポップアップストアを渋谷公園通り店で展開するということで、メインディスプレイを全部僕がやらせていただいて。それからも、不定期ですがBEAUTY&YOUTHさんをはじめ、ユナイテッドアローズさんとも色々お仕事させていただいてます。
-実際スケシンさんにお会いしていかがでした?
松崎: すごく楽しい人ですね。お互い妥協しない性格なので何回も打ち合わせして、ここまでやりましょうって意気投合しないと、GOしないんです(笑)。家電の演出をするときはとことん詰めますね。こういうのをやったら面白いんじゃないか、とか。今年もまた何か違う形でご一緒できればいいなと思っています。
-ディスプレイの仕事を機に急速的に広がりましたね。
松崎: 本当にそう思います。家電蒐集の前がディスプレイや展示の仕事が本業だったので、家電を集めてどう見せたら面白いのか考えるのが楽しいんです。僕はコレクターではないので、集めて、それを現代にどう活かせるか、活かすか、というのを考える方が好きで。そういう意味では、昔の仕事と今の仕事が上手く融合して現在に至っていますね。
-22年間の会社勤めは決して無駄ではなかったと。
松崎: その経験が基本的にベースにあって、家電蒐集の仕事に結びついていますね。現在も色々とプロジェクトを進行中なんですけど、全部インテリアとディスプレイが連動していて、集めた家電やサイズとかも向こうの担当の方と図面を見ながらレイアウトを考えたりとか、その場で全部できちゃうので。昔のことが活きている証拠ですね。
-進行中のプロジェクト、聞いてもいいですか?
松崎: 大きなプロジェクトで言うと、2013年6月に東京ガスの大型ショールームが、横浜みなとみらいにできるんですね。その中に「比べるハウス」というのを作っていて、現代の家の快適さと80年代の家の快適さを比較するというものなんです。この実体験型ハウスは、当時の部屋ってこうだったっけ、なんか快適じゃないな、みたいなのを80年代の部屋に入って感じてもらう。その次に現代の部屋に入って、今のテクノロジーはこんなに進化して快適なんだ、というのを体感してもらうという。僕はその中の80年代家電のセレクトを全部任せてもらっているんです。ちゃんと家族構成があって、ポットとか冷蔵庫も主人はこういう趣味でこうだから......とか、子供の趣味はこうだからファミコンのソフトはコレとか。そういうのを生活の中に落とし込んでから家電をセレクトしています。今ちょうど集めていて、ちゃんと使える状態にして納品するんです。
-かなり細かいですね。
松崎: そうなんです。家族の趣味趣向が分かって、かつ良いものをセレクトして提案するんです。その方がより当時のリアル感が増すでしょ。あと、テレビ局とかドラマの演出の仕事も増えましたね。ドラマの中で昔の家電が必要とされることって結構多くて。80年代のドラマを再現することとかよくあるじゃないですか。でも昔の家電って調達する人がいないんですよ。現代だったら何でも揃いますけど、さすがに当時の細かい家電までは舞台美術屋さんには残っていないみたいで。そうすると僕のところに来るんです。ちょうど2年前にフジテレビで80年代に起こった大韓航空機爆破事件の特番があったんですけど、事件の犯人(金賢姫)が機内に仕掛けた爆弾っていうのが、当時の〈パナソニック〉のポータブルラジオで。その再現ドラマを作るために、犯人が仕掛けたラジオから、彼女が泊まったホテルのテレビや家電を全部集めました。
-見つかりました?
松崎: はい。テレビ局内では誰もが無理だって言っていたそうなんですが、一週間で同型のものを見つけました(笑)。あとバラエティ系で言えば「アメトーーク」とか。家電芸人特集で、芸人たちが昔使っていた家電を集めてスタジオに持っていく仕事とか。もう家電を使う仕事であればなんでもって感じですね(笑)。
-集められない不安とかはないんですか?
松崎: ないですね。結局、そのネットワークを作ることだけに1年間費やしているので。だから家電蒐集に関しては誰にも負けないという自負があるんです。僕に集められなければ誰も集められない。僕が直せないものは他でも直せない。今、修理だけも膨大な依頼数で。メーカーでも断られちゃった家電を専門に直しているんです。90年代から使っていた大きな電卓がすごく使いやすくて、たまたまそれにコーヒーをこぼしちゃったらしいんですよ。それで依頼を受けて、直るでしょうかって。ちゃんと直りましたよ。
-家電なら直らないものはないと。
松崎: そうです。うちで直せないものはどこも直せない。そのぐらいまで技術とか、直せる確率というのはダントツでトップです。元々やりたかったというよりは、いろいろな方からの要望がものすごく多くて。だったら修理センターを作りますって。でも僕ひとりだけではできないので、修理のスペシャリストがいる会社と組んで。僕のノウハウとその会社のノウハウを足して。新たに「DESIGN UNDERGROUND」で修理センターを作ったんです。僕がやりたいというよりは、いつの間にかそうなっちゃったみたいな(笑)。
-でも他にできる人がいないわけですし、ある意味自然な流れですよね。
松崎: そうですね。家電のスタイリストやコーディネイト、ディスプレイにしても、いろいろな方から依頼がくるので。結局、それを形にして、こういうことをやったほうが面白いんじゃないか、というのは僕からも提案しています。もっとたくさんの人と一緒に、家電にまつわることをやっていきたいですね。実は6月に青幻舎から僕の集めている家電カタログの中から、すごくユニークな家電を抜粋した家電バイブルを出す予定で。数万点の中から400点に絞って、A5版くらいのサイズで400ページくらい。ラジカセを含め、黄金期と呼ばれた70年代~80年代の日本製家電を網羅しています。
-"蒐集家のとしての喜び"って何ですか?
松崎: ひとつは蒐集家としての物との出合いの楽しみ。アマチュア無線の話をしましたけど、全然知らなかった方と偶然知り合える喜びというか。その喜びが物と対話すること、発見することが喜びなんですよ。だから形は変われど、やることは変わっていないんです。探しに行って、物との出合いを毎日楽しんでいる。それが一つの喜びなんですね。今日はこんなものをゲットできたというのが。あと、その集めた物を発見したときは死んでいる状態ですよ。それを僕が手を入れることによって、新たな命を吹き込んだときに、動いた、生き返ったというときの喜び。新たな命を宿すことができる、それがすごく楽しい。新たな命を吹き込むのって、お医者さんが患者さんを治すのと一緒で、本来あるべき姿に戻してあげるっていう、まさに修理人としての醍醐味ですよね。その上で探して出合う楽しみ、直して復活したときの喜び、そしてもう一つは直したものをもう一回世の中に出したい。今まで家電が持っていたイメージではなくて、新たな文脈を僕が作ってあげたい。2013年にどう活かせるか、というのを僕が提案したいんです。
-ジャンク品として終わらせず、何かしらの付加価値を付けて提案すると。
松崎: そうです。これまで知り合った方と話をしていくうちに、じゃあこういうことをやってみませんかとか、話しているうちに僕もアイデアが生まれるし、相手のほうも家電ってそういう使い方もあるのかって面白がってくれて。そこからまた新たなコンテクストが生まれるんですよ。これから未来に向けて、古い家電をどういう風に活かしていくのかを、色んなアプローチで提案していきたいですね。